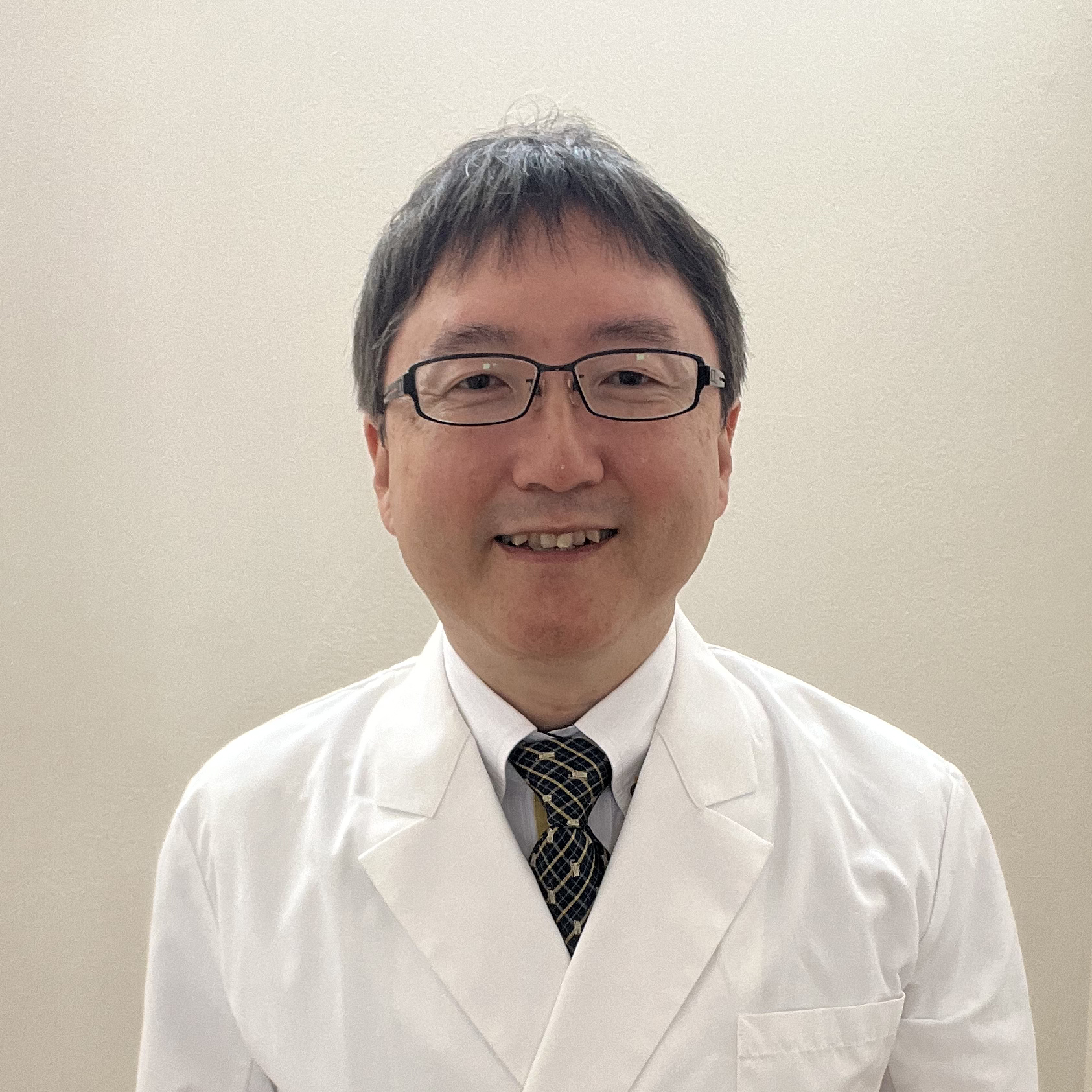体が疲れやすいと感じる原因は?改善法と考えられる病気を解説

最近、「しっかり寝ても疲れがとれない」「以前より疲れやすくなった」と感じていませんか?
その疲れやすさの原因は、生活習慣の乱れやストレスだけでなく、思わぬ病気が隠れているサインかもしれません。放置すると、心身の不調につながる可能性もあります。
この記事を読めば、ご自身の疲れの原因を見極め、今日からできる具体的な対処法を実践できます。
【この記事でわかること】
・疲れやすさの主な原因(生活習慣・ストレス・病気)
・日常生活でできる具体的な疲れのセルフケア方法
・女性特有の疲れやすさの原因
・病院を受診すべき症状の目安と診療科
体が疲れやすくなる主な原因
この章のまとめ!
疲れやすさの背景には、睡眠不足や栄養の偏りといった「生活習慣の乱れ」が大きく関わっています。また、身体的な原因だけでなく、精神的なストレスや、貧血・甲甲状腺機能低下症などの「病気」が隠れている可能性も考慮する必要があります。
ここでは、体が疲れやすい主な原因について、一つひとつ詳しく見ていきましょう。
原因① 生活習慣の乱れ
睡眠不足や不規則なリズムは、心身を回復させる自律神経の働きを乱します。また、エネルギー産生に必要なビタミンB群や鉄分、タンパク質が不足すると、体は活力を生み出せません。
運動不足による筋力低下や血行不良も疲労物質を蓄積させます。日常的に十分な水分を摂らないことも、血流を悪化させ疲労感を増幅させる一因となるのです。
原因② 過度なストレス
仕事や人間関係などの精神的なプレッシャー、あるいは過労や気温の変化といった身体的ストレスは、自律神経のバランスを崩します。特に、体を活動的にする交感神経が優位な状態が続くと、心と体は常に緊張を強いられ、十分に休むことができません。
この絶え間ない緊張状態がエネルギーを過剰に消耗させ、慢性的な疲労感につながるのです。
原因③ 病気のサイン
なかなか取れない疲れは、特定の病気が原因かもしれません。
例えば、貧血や甲状腺機能の低下、糖尿病などは、体のエネルギー代謝に異常をきたし、強い倦怠感を引き起こします。他にも睡眠時無呼吸症候群やうつ病なども考えられます。
以下の表で、疲れ以外の症状も確認し、当てはまるものがあれば医療機関の受診を検討してください。
| 病名 | 疲れ以外の主な症状 |
|---|---|
| 貧血 | めまい、立ちくらみ、動悸、息切れ、顔色が悪い |
| 甲状腺機能低下症 | 体のむくみ、寒がり、体重増加、便秘、気力の低下 |
| 糖尿病 | 喉の渇き、頻尿、体重減少 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | いびき、日中の強い眠気、起床時の頭痛 |
| うつ病 | 気分の落ち込み、興味・関心の喪失、食欲不振、不眠 |
| 副腎疲労 | 朝起きられない、倦怠感、集中力の低下、甘いものが欲しくなる |
原因④ 女性特有のホルモンバランスの変化
女性はライフステージの変化に伴い、特有の疲れを感じやすいです。月経前はホルモンの変動でだるさを感じ、経血により鉄分が失われ貧血気味になることもあります。妊娠・出産期は体に大きな負担がかかり、産後の育児も疲労を蓄積させます。
また、更年期には女性ホルモンが減少し、自律神経が乱れることで、これまでとは違う質の倦怠感に悩まされるのです。
☝️簗先生の一言アドバイス!
「女性特有の疲れは、一人で抱え込まずに婦人科へ相談することも大切です。特に、月経の量が多い方や、更年期のような症状があるときは、専門医のアドバイスで楽になることがありますよ。」
【改善法】疲れにくい体をつくるセルフケア
この章のまとめ!
疲れにくい体を作るためには、「バランスの取れた食事」「質の高い睡眠」「適度な運動」という3つの柱が不可欠です。これらを日常生活にうまく取り入れることが、根本的な体質改善への第一歩となります。
自分の疲れのタイプが把握できたら、具体的な行動に移しましょう。ここでは、毎日の生活の中で意識できる、疲れにくい体をつくるための3つの基本的なセルフケア方法をご紹介します。
食事の見直し:エネルギーを生み出す栄養素を摂る
エネルギー産生を助けるビタミンB群(豚肉や玄米)、血液の材料となる鉄分(レバーやほうれん草)、そして体を作るタンパク質(肉、魚、大豆製品)を意識して摂取しましょう。
1日3食を規則正しく、野菜から先に食べることで血糖値の急上昇を抑えることも有効です。まずは、普段の食事に1品加えることから始めて、栄養バランスを整えていきましょう。
☝️簗先生の一言アドバイス!
「忙しい方は、まずコンビニでサラダチキンやゆで卵、野菜ジュースを1品加えることから始めてみましょう。小さな工夫でも、継続することが大切ですよ。」
睡眠の質を高める:心と体をしっかり休ませる
毎日決まった時間に起き、太陽の光を浴びることで体内時計をリセットしましょう。就寝1〜2時間前の入浴は、自然な眠りを誘います。
逆に、寝る前のカフェイン摂取やスマートフォンの使用は、脳を覚醒させてしまうため控えるべきです。寝室の環境を暗く静かに整え、自分に合った寝具を選ぶことも、深い眠りのためにはとても大切な要素となります。
以下の記事では睡眠の質が悪いと体にどのような変化が起こるのか、詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
適度な運動を取り入れる:体力と血流をアップする
運動は体力や筋力を向上させるだけでなく、血行を促進して疲労物質の排出を助けます。また、心地よい疲労は睡眠の質を高め、ストレス解消にもつながります。まずは1日20分程度のウォーキングから始めてみましょう。
日常生活でエスカレーターを階段に変えるなど、少しの工夫でも運動習慣をつくることは可能です。継続することで体は確実に変わっていきます。
セルフケアで改善しない…病院へ行くべき目安
この章のまとめ!
セルフケアを1ヶ月ほど試しても疲れが改善しないときや、日常生活に支障が出るほどの強い倦怠感があるときは、医療機関の受診を検討しましょう。まずはかかりつけの内科、または症状に合わせて専門の診療科を選ぶことが大切です。
生活習慣を見直しても不調が続くときは、専門家の助けを借りるサインです。ここでは、病院を受診すべき症状の目安と、何科にかかればよいのか、具体的な指針をお伝えします。
受診を検討すべき症状(サイン)
セルフケアを続けても改善が見られないときは、病気が隠れているかもしれません。以下のリストに当てはまる項目があるなら、医療機関への受診を考えてください。
・十分な休養をとっても、1ヶ月以上疲れが続く
・日常生活に支障が出るほどの強い倦怠感がある
・めまい、立ちくらみ、動悸、息切れなどを伴う
・原因不明の体重減少や発熱がある
・気分の落ち込みが激しく、何もやる気が起きない
何科を受診すればいい?
どの科に行けば良いか迷うなら、まずは「内科」か「総合診療科」を受診するのが適切です。ここで症状を総合的に診てもらい、原因を探ります。その上で、より専門的な検査や治療が必要と判断されれば、適切な診療科を紹介してもらえます。
月経不順があれば婦人科、気分の落ち込みが強ければ心療内科など、特定の症状に応じて選ぶこともできます。
病院で伝えるべきこと
診察の際は、医師に正確な情報を伝えることが診断の助けになります。いつから、どのような疲れがあるのか、疲れ以外の症状、生活習慣の変化やストレスの有無などを具体的に話しましょう。
現在服用している薬やサプリメントがあれば、お薬手帳などを持参して見せるのが確実です。事前にメモを準備しておくと、伝え忘れを防ぐことができます。
体の疲れやすさに関するよくある質問
Q. 疲れやすさと肝臓の機能は関係ありますか?
A. はい、関係があります。肝臓は栄養素の代謝や解毒を行う重要な臓器であり、機能が低下するとエネルギーが作られにくくなったり、疲労物質が溜まりやすくなったりして、疲れやだるさを感じることがあります。
ただし、肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、症状が出にくいのが特徴です。お酒をよく飲む方や、健康診断で肝機能の数値を指摘された方は、一度内科で相談してみましょう。
Q. 女性ホルモンの乱れによる疲れやすさはどうすれば改善できますか?
A. まずはバランスの取れた食事、質の良い睡眠、適度な運動といった基本的な生活習慣を整えることが大切です。症状が辛いときは、婦人科でホルモン補充療法(HRT)や漢方薬の処方など、専門的な治療を受けることもできます。
Q. ストレスで疲れやすくなるのはなぜですか?
A. ストレスを感じると、体は対抗するために自律神経のうち交感神経を活発にし、常に緊張状態になります。この状態が続くと、心身が休まらずエネルギーを消耗し続け、疲労が蓄積してしまいます。
また、ストレスは睡眠の質を低下させたり、ホルモンバランスを乱したりすることでも、疲れやすさの原因となります。リラックスできる時間を持つことが大切です。
Q. 疲れに効くサプリメントはありますか?
A. 食事で不足しがちな栄養素を補う目的で、ビタミンB群や鉄などのサプリメントを利用するのも一つの方法です。
ただし、サプリメントはあくまで食事の補助です。まずは食事内容を見直すことが基本であり、サプリメントを摂取するなら、過剰摂取に気を付け、かかりつけ医や薬剤師に相談することをおすすめします。
Q. 20代なのに疲れやすいのはなぜでしょうか?
A. 20代で疲れやすいのは、不規則な生活習慣が大きく影響していることが多いです。
例えば、就職や進学による生活リズムの変化、友人との夜更かし、栄養の偏った食事、運動不足などが考えられます。また、新しい環境での人間関係や仕事のプレッシャーといった精神的なストレスも原因となり得ます。まずはご自身の生活習慣を見直してみましょう。
まとめ
この記事では、疲れやすさの原因から具体的な対処法までを解説しました。最後に、大切なポイントを振り返ります。
・疲れの原因は主に「生活習慣」「ストレス」「病気」「ホルモンバランス」の4つ
・「食事・睡眠・運動」の生活習慣を見直すことがセルフケアの基本
・1ヶ月以上続く疲れや、他の症状があるときは迷わず医療機関へ
疲れは、体からの大切なサインです。
本記事が、健やかな日々を過ごすための参考になればと思います。