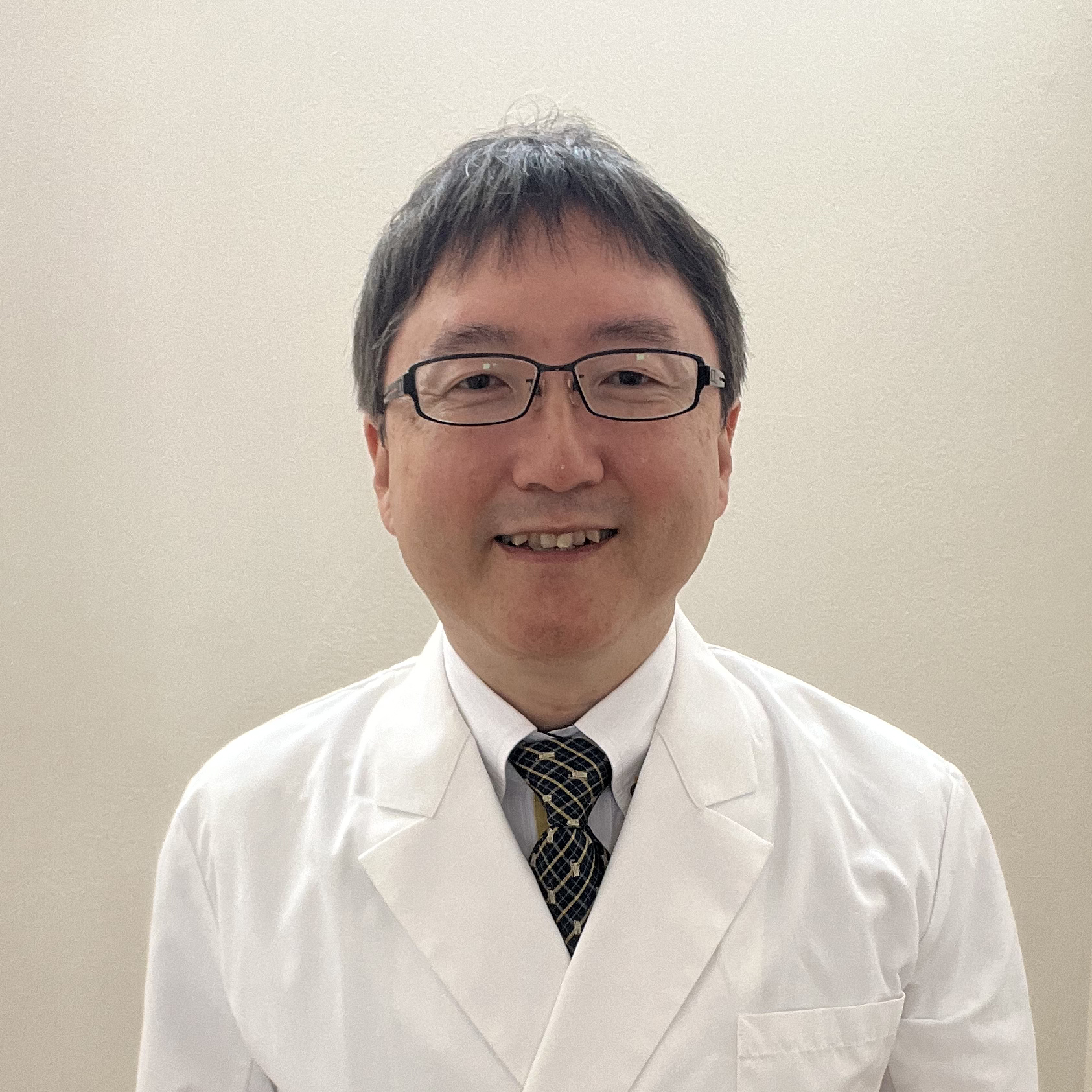お酒によるむくみの原因は?予防法・解消法を解説

お酒を楽しんだ翌朝、「顔がパンパン」「足が重い」と感じたことはありませんか?
その原因は単なる飲みすぎではなく、アルコールの作用と生活習慣によって水分バランスが乱れることにあります。
しかし、正しい知識とケアを身につければ、むくみを防ぎながらお酒と上手につき合うことが可能です。
◯本記事でわかること
・お酒を飲むとむくみやすくなる4つのメカニズム
・お酒によるむくみがどれくらい続くか、放置してよいケースと医療機関に相談すべきサイン
・むくみが出やすい顔・足それぞれの部位別セルフケア
・飲む前・飲んでいる最中・飲んだ後にできるむくみ予防の具体策
・むくみにくいお酒・おつまみと、避けたい組み合わせ
・むくみ対策に役立つ食べ物・飲み物・栄養素
日常のちょっとした習慣が、翌朝のコンディションを左右します。 「むくまない飲み方」を知り、すっきりとした毎日を過ごしましょう。
お酒を飲むとむくむ4つの原因
この章のまとめ!お酒によるむくみの主な原因は、アルコールの作用による水分の排出と、その後の身体の防御反応。塩分の多いおつまみも、むくみを悪化させる大きな要因。
お酒を飲むと顔や体がむくむのは、体内の水分バランスが乱れるからです。その背景には、アルコールそのものの作用や、飲酒時の行動が関係する複数の原因があります。
原因①アルコールの利尿作用が招く「脱水」と「水分の溜め込み」
アルコールには高い利尿作用があり、飲んだ量以上に尿として水分を排出させます。すると体は水分不足(脱水状態)に陥り、生命維持のために残った水分を溜め込もうと働きます。この防御反応が、血管の外に水分を漏れ出させ、むくみという症状を引き起こすのです。そのため、飲酒中はこまめな水分補給が欠かせません。
原因②血中アルコール濃度の上昇による「血管の拡張」
アルコールが分解される過程で生じるアセトアルデヒドには、血管を拡張させる作用があります。血管が広がると血流が緩やかになり、血管の壁から水分が漏れ出しやすくなります。特に、顔のように皮膚の薄い部位ではその影響が現れやすく、赤ら顔やむくみの原因となります。これもむくみを引き起こす一因です。
原因③おつまみは要注意!「塩分の摂りすぎ」
お酒と一緒につい食べてしまう塩辛いおつまみは、むくみの大きな原因です。体内の塩分濃度が上がると、体はそれを薄めようとして水分を溜め込みます。アルコールによる水分の溜め込みと塩分による作用が合わさることで、むくみはさらに悪化します。おつまみ選びが翌朝のコンディションを左右するのです。
原因④意外な落とし穴「長時間の同じ姿勢」
居酒屋やバーなどで長時間座ったままの姿勢でいることも、むくみを助長します。特に足は心臓から遠く、重力の影響で水分が溜まりやすい部位です。動かないことでふくらはぎのポンプ機能が働かず、血行不良に陥ります。これが、お酒を飲んだ翌日に足が重く感じたり、パンパンになったりする理由の一つです。
お酒によるむくみはいつまで続く?放置は危険?
この章のまとめ!お酒によるむくみは通常1日程度で治まるが、2日以上続くときは注意が必要。息苦しさや極端な体重増加を伴うむくみは、病気のサインの可能性がある。
飲酒後のむくみがいつまで続くか、気になりますよね。ほとんどは一過性ですが、まれに注意が必要なケースもあります。ここでは、むくみが続く期間と危険なサインを解説します。
通常は半日〜1日で自然に解消されることが多い
お酒が原因の一時的なむくみは、体内のアルコールが分解され、水分バランスが正常に戻るにつれて解消に向かいます。個人差はありますが、一般的には半日〜1日程度で自然に治まることがほとんどです。そのため、翌日に水分をしっかり摂り、安静にしていれば過度な心配は不要です。まずは体を休めることを優先しましょう。
【要注意】2日以上むくみが続く場合に考えられること
もしむくみが2日以上続くときは、単なるお酒の影響ではないかもしれません。肝臓や腎臓の機能が低下していると、アルコールの分解や水分の排出がうまくできず、むくみが長引くことがあります。特に、飲酒習慣がある人でむくみがなかなか引かない状況が続くなら、一度、内科や専門の医療機関で相談することをおすすめします。
病気のサイン?受診が必要なむくみの特徴
むくみに加えて特定の症状が現れたら、すぐに医療機関を受診してください。心臓、腎臓、肝臓などの重大な病気が隠れている可能性があります。以下の特徴をセルフチェックし、一つでも当てはまるなら自己判断せず医師に相談しましょう。
| 特定の症状 | 考えられる病気の例 |
|---|---|
| 息苦しさ、横になると咳が出る | 心不全 |
| 体重の急激な増加(2〜3日で2kg以上) | 腎不全、ネフローゼ症候群 |
| 片足だけが極端にむくみ、痛む | 深部静脈血栓症 |
| 皮膚や白目が黄色くなる(黄疸) | 肝硬変などの肝機能障害 |
| 指で押した跡がなかなか戻らない | 腎臓や心臓の病気の可能性 |
【部位別】顔・足のむくみを解消するセルフケア
この章のまとめ!顔や足のむくみには、滞ったリンパや血液の流れを促すケアが有効。マッサージやストレッチで物理的に水分を流し、血行を促進することで、素早い解消が期待できる。
つらいむくみを今すぐどうにかしたいですよね。特に気になる「顔」と「足」に焦点を当て、自宅で簡単にできるセルフケア方法をご紹介します。
【顔のむくみ】3分マッサージ
顔のむくみは、リンパの流れを意識したマッサージが効果的です。
◯マッサージの手順とポイント
・STEP 1(準備):リンパの通り道を作る
耳の下から首筋を通って、鎖骨のくぼみに向かって指全体でやさしくなでおろします。これを数回繰り返して、リンパの流れを整える土台をつくります。
・STEP 2(実践):顔の水分を外側へ流す
額・頬・あごなどの顔の中心から、こめかみや耳の前へ向けて、水分を移動させるように優しくマッサージします。皮膚の表面をなでるような力で十分です。
・STEP 3(仕上げ):鎖骨のリンパ節へ流し込む
STEP1と同じ動きを繰り返し、顔から集めた余分な水分を首筋から鎖骨にしっかり流し込みます。
◯全体の注意点
- 力を入れすぎないようにしましょう。
- 肌表面をやさしくなでるだけでも効果があります。
- オイルやクリームを使うと摩擦が減り、より快適に行えます。
【足のむくみ】重だるさを解消する簡単ストレッチ
足のむくみには、ふくらはぎのポンプ機能を活性化させるストレッチがおすすめです。椅子に座ったまま、かかとを床につけてつま先を上げ下げしたり、足首を大きく回したりするだけでも血行が改善します。また、寝る前に仰向けになり、両足を壁に立てかける「足上げ」も、足に溜まった水分を戻すのに役立ちます。
血行を促進する「蒸しタオル」と「温冷シャワー」
血行促進はむくみ解消の鍵です。水で濡らして絞ったタオルを電子レンジで温めて蒸しタオルを作り、首や肩に当てると顔周りの血行が良くなります。また、足には温かいシャワーと冷たいシャワーを交互にかける「温冷交代浴」がおすすめです。血管が収縮と拡張を繰り返し、ポンプのように血流を促してくれます。
☝️簗先生から一言アドバイス!
マッサージは気持ち良いと感じる程度の力加減で行いましょう。強くこすると肌を傷つけたり、摩擦によってシミの一種である肝斑を悪化させたりすることもあるので注意が必要です。あくまで優しく、が基本です。
お酒の席でできるむくみの予防法
この章のまとめ!お酒によるむくみを防ぐには、飲む前から対策を始めることが重要。水分補給を基本に、むくみにくいお酒やおつまみを選び、体内の水分と塩分のバランスを意識する。
むくみを解消するのも大切ですが、そもそもむくまないように心がけることが一番です。ここでは、お酒を飲む「前」「最中」「後」のタイミング別に、誰でも実践できる予防法を解説します。
【飲む前に】空腹を避けて、まずはコップ一杯の水を飲む
空腹状態でお酒を飲むと、アルコールの吸収が早まり、血中アルコール濃度が急上昇してしまいます。飲む前には何か軽くお腹に入れておきましょう。また、あらかじめコップ一杯の水を飲んでおくことも大切です。体内の水分量を満たしておくことで、アルコールの利尿作用による急激な脱水を和らげる効果が期待できます。
【飲んでいる最中に】むくみにくいお酒とおつまみの選び方
お酒の種類やおつまみを意識的に選ぶことで、むくみを大きく軽減できます。糖質が少なく利尿作用が穏やかな蒸留酒を選び、塩分を排出するカリウムが豊富なおつまみを組み合わせるのが賢い選択です。以下のリストを参考にしてみてください。
| おすすめ(むくみにくい) | 避けたほうが良い(むくみやすい) | |
|---|---|---|
| お酒 | ウイスキー、焼酎、ジンなどの蒸留酒 | ビール、日本酒、ワインなどの醸造酒 |
| おつまみ | 枝豆、アボカド、きゅうり、海藻サラダ | 漬物、塩辛、フライドポテト、ラーメン |
【飲んだ後に】寝る前に実践したい2つのこと
お酒を飲んだ日の夜は、寝る前のちょっとした工夫で翌朝のむくみ具合に差が出ます。アルコールの影響で脱水と血流の変化が起きやすくなるため、それを和らげるための対策を取り入れることが大切です。
・水分をしっかり補う 飲酒後は体が脱水状態になりやすいため、飲んだお酒と同量程度の水を飲んでから就寝するのが理想です。体内の水分バランスを整えることで、アルコールによるむくみを抑えやすくなります。
・枕の高さを少し上げる 顔が心臓よりも高い位置になるように枕を調整することで、余分な水分が顔にたまるのを防ぎます。翌朝の顔のむくみが気になる方におすすめです。
むくみ解消をサポートする食べ物・飲み物
この章のまとめ!むくみ解消には、体内の余分な塩分を排出する「カリウム」を摂取することが効果的。カリウムは多くの野菜や果物に含まれており、日々の食事に手軽に取り入れられる。
セルフケアと合わせて、食事による内側からのケアも行いましょう。むくみの原因となる塩分を排出し、体の調子を整える栄養素を積極的に摂ることが大切です。
体内の余分な塩分を排出する「カリウム」が豊富な食品
カリウムは、体内のナトリウム(塩分)と水分を一緒に尿として排出してくれる、むくみの強い味方です。特に、野菜や果物に多く含まれています。日常の食事に以下の食材をプラスすれば、むくみ対策につながるでしょう。
・果物: バナナ、キウイフルーツ、アボカド、メロン
・野菜: ほうれん草、きゅうり、かぼちゃ、トマト
・その他: 海藻類(わかめ、昆布)、きのこ類、芋類
肝臓の働きを助ける「タウリン」を含む食品
アルコールの分解を一手に担うのが肝臓です。肝臓の働きが弱ると、アルコールの分解が遅れ、むくみが長引く原因にもなります。タコやイカ、ホタテなどの魚介類に多く含まれるタウリンは、肝機能をサポートする栄養素です。おつまみとして、タコのカルパッチョなどを選ぶのも良いでしょう。
コンビニでも手軽に買える!おすすめの飲み物
むくみ対策には、利尿作用のあるカフェインを含まない飲み物が適しています。特に、ミネラルが豊富でノンカフェインの麦茶やルイボスティーは、水分補給に最適です。また、コーン茶もカリウムを含み、むくみ解消に良いとされています。これらはコンビニでも手軽に購入できるので、日頃から意識して選んでみましょう。
☝️簗先生から一言アドバイス!
カリウムは水に溶けやすい性質があるので、調理方法を検討しましょう。生で食べられる果物やサラダ、または煮汁ごと栄養を摂れるスープやお味噌汁などで摂取すると、効率よく体内に取り込めますよ。
お酒とむくみに関するウソ?ホント?
この章のまとめ!むくみ解消の俗説には、かえって体を危険に晒すものもある。サウナでの無理な発汗は脱水を悪化させ、サプリメントはあくまで補助的なものと理解することが重要。
お酒のむくみに関しては、さまざまな情報が飛び交っています。正しい知識を身につけましょう。
「サウナで大量に汗をかけばむくみは抜ける」は本当?
これは危険な誤解です。お酒によるむくみの根源は「脱水」にあるため、サウナでさらに汗をかくと脱水症状が悪化し、体はもっと水分を溜め込もうとします。血圧の急変動など体への負担も大きく、非常に危険です。飲酒後のサウナは絶対に避け、まずは常温の水を飲んで体を潤すことを最優先してください。
「むくみ解消サプリメント」は効果があるの?
市販のサプリメントは、カリウムなどむくみ解消をサポートする成分を含むものが多いですが、医薬品のような治療効果が保証されているわけではありません。頼りすぎるのではなく、食生活や運動習慣の改善を基本とした上で、補助的に利用することを検討するのが良いでしょう。
お酒のむくみに関するよくある質問
最後に、お酒のむくみに関してユーザーから寄せられることの多い質問にお答えします。日頃の小さな疑問を解消して、むくみへの不安をなくしましょう。
Q1.ワインとビール、むくみやすいのはどっちですか?
A. 一概には言えませんが、ビールの方がむくみやすい傾向にあります。ビールはゴクゴクと飲む量が多くなりがちで、塩分の多いおつまみと合わせることが多いからです。また、どちらも醸造酒であり、蒸留酒に比べると糖質なども多く含むため、むくみやすいお酒のカテゴリに入ります。飲む量を意識することが大切です。
Q2.漢方薬を試してみたいのですが、おすすめはありますか?
A. 体内の水分バランスを整える漢方薬として「五苓散(ごれいさん)」が有名で、二日酔いやむくみに用いられることがあります。ただし、漢方薬は個人の体質に合わせて選ぶことが非常に重要です。自己判断で選ばず、まずは漢方に詳しい医師や薬剤師に相談し、ご自身の体質に合ったものを処方してもらうようにしましょう。
まとめ
お酒によるむくみの原因から、ご自身でできる解消法・予防法まで解説しました。むくみを正しく理解し、適切に対処すれば、お酒と上手に付き合っていくことができます。最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。
・お酒のむくみは、アルコールの利尿作用による「脱水」と、塩分の摂りすぎによる「水分の溜め込み」が主な原因です。
・顔や足のむくみには、リンパや血液の流れを促すマッサージやストレッチが即効性があり効果的です。
・予防が最も重要で、「飲む前の水分補給」「カリウム豊富なおつまみ」「寝る前の水分補給」を意識しましょう。
・むくみが2日以上続く、または息苦しさなどの症状を伴うときは、迷わず医療機関を受診してください。
正しい知識を身につければ、むくみを過度に恐れる必要はありません。ご自身の体と相談しながら、上手にお酒を楽しんで、すっきりとした毎日をお過ごしください。